

Monthly Report of the Jupiter-Saturn Section, November, 2003
課長 堀川 邦昭 K.Horikawa 幹事 伊賀 祐一 Y.Iga
木星は夜半過ぎには東天に昇るようになった。 今月は下記の観測者から報告を受けている。 今月から大田氏、鈴木氏、福井氏、三品氏に新たな報告者として加わっていただいた。 各氏とも月惑星研究会関西支部の常連であり、今後の活躍に期待したい。 また、前課長の宮崎氏は3年ぶりに観測を再開されたとのことで、9月以降の観測をまとめてお送りいただいた。
| 阿久津富雄 | (栃木県) | 32cm反赤 | CCD画像7 |
| 池村 俊彦 | (愛知県) | 31cm反赤 | CCD画像8 |
| 永長 英夫 | (兵庫県) | 25cm反赤 | CCD画像33 |
| 大田 聡 | (沖縄県) | 32cm反赤 | CCD画像1 |
| 風本 明 | (京都府) | 31cm反赤 | CCD画像2 |
| 鈴木 隆 | (東京都) | 18cmMC赤 | CCD画像1 |
| 中西 英和 | (愛知県) | 30cm反赤 | CCD画像2 |
| 成田 広 | (神奈川県) | 20cm屈赤 | スケッチ4枚 |
| 福井 英人 | (京都府) | 25cm反赤 | CCD画像19 |
| 堀川 邦昭 | (神奈川県) | 16cm反赤 | スケッチ9枚、CCD画像5 |
| 三品 利郎 | (神奈川県) | 20cm反赤 | CCD画像1 |
| 宮崎 勲 | (沖縄県) | 40cm反赤 | CCD画像27 |
| 森田 光治 | (滋賀県) | 20cm反赤 | CCD画像1 |
| 柚木 健吉 | (大阪府) | 20cm反赤 | CCD画像3 |
| 米山 誠一 | (神奈川県) | 20cm反赤 | CCD画像2 |
| Ng, Eric | (香港) | 30cm反赤 | CCD画像1 |
| Sherrod, P. Clay | (米国) | 31cmSC赤 | CCD画像16 |
mid-SEB outbreakの活動にやや変化が見られる。 9〜10月の発生源の位置は体系II:190〜195°付近にありほぼ一定であったが、11月に入るとしだいに前方へ移動し、体系II:169°(25日、福井氏)に達している。 2002年12月に発生した前回のoutbreakでは、約3ヶ月ほど活動が続いた後、2003年3月に発生源での白斑の供給が途絶え、白雲領域が後方から急速に縮小して活動の終わりを迎えた。 今回のoutbreak発生を8月と仮定すれば、ちょうど3ヶ月が経過しており、活動が終息に向かっていると見ることもできるが、発生源の前進速度は-1°/dayに満たず、前回よりもかなり小さく、11月後半は体系II:170°付近で停滞していると見ることもできる。 また、体系II:250°付近のSEB中央部には赤みを帯びた小暗斑がシーズン初めから観測されているが、今月は前方のSEBnが淡化して明帯が形成されている。 このため、mid-SEB outbreak後端の位置がつかみづらくなっている。 他の経度のSEBは中央組織から北縁までのベルトの北半分が濃く顕著であるが、高解像度の画像では、前述の小暗斑後方のSEBn内部に泡粒状の白斑が多数見られる。
RSは体系II:91.4°(25日、宮崎氏)にありオレンジ色が顕著である。 南縁にアーチは存在しないが、月初と月末には後端が暗条によってSEBと連結されていた。 BAは体系II:207.0°(6日、福井氏)に位置している。 周囲に薄暗い縁取りが見られるが、輝度はなく周囲とのコントラストは低い。 濃く幅広いSTBは体系II:270〜320°の区間のみであるが、その後方でもやや南寄りの位置にSTBsと見られる細い組織が体系II:20°付近まで伸びている。 他にこの緯度で目につく模様としては、RS後方の小暗斑(体系II:138.9、6日、中西氏)、BA直後の暗部、前述のSTB暗部の直前に見られる暗斑(体系II:248.8°、21日、Sherrod氏)などがあげられる。 STBの南、南緯35〜47°の範囲には3つの組織が認められ、ベルトの命名に苦しむ。 このうち、中央の南緯38〜41°に見られるのが真のSSTB(体系II:50〜130°、280〜0°など)で、南緯35〜37°の組織はSTZB(180〜280°)、南緯42〜47°のものは(S)SSTB(0〜90°など)と思われる。 SSTBの小白斑は今シーズンも偏った経度範囲に分布している。 昨シーズンは5個が約90°の範囲に見られたが、今月は体系II:140〜200°の間に4つ見られ、もうひとつは少し離れて体系II:110°付近に位置している。
EZは北半分が軽く黄濁し、NEB南縁に青黒い暗部を伴ったfestoonが多数見られるが、体系I:100°台は比較的静かでfestoonも目立たない。 NEB内部はrift活動や不規則な白斑が多数存在し、近年になく活動的である。 そのため、かなりの経度でベルトが二条になっている。 これらの模様は体系IIに対してかなり速いスピードで前進しているようである。 ベルト北縁は概ね平坦で顕著なbargeはほとんど見られないが、体系II:100°台ではかなり起伏があり乱れている。
NTB以北は静かで特に変化は見られない。 NNTB北縁となる北緯36°付近では、体系II:200°前後にいくつかの小暗斑が散在している。 昨シーズン当課ではNNTBsのジェットストリームに乗った暗斑を9個(平均9h53m55.2s±4.8s)捉えており、これらについても同種の模様であることが疑われるが、確認するに至っていない。
来年元旦の衝を控え、土星は観測の好機を迎えている。 今月は下記の観測者から報告が寄せられている。 木星と同様、月惑星研究会関西支部から阿久津弘明氏、大田氏、菅野氏、根市氏、福井氏を新たな報告者として迎えている。
| 阿久津富雄 | (栃木県) | 32cm反赤 | CCD画像4 |
| 阿久津弘明 | (北海道) | 28cm反赤 | CCD画像11 |
| 池村 俊彦 | (愛知県) | 31cm反赤 | CCD画像16 |
| 大田 聡 | (沖縄県) | 32cm反赤 | CCD画像5 |
| 風本 明 | (京都府) | 31cm反赤 | CCD画像2 |
| 菅野 清一 | (山形県) | 25cm反赤 | CCD画像2 |
| 中井 健二 | (広島県) | 25cmMC赤 | CCD画像1 |
| 根市 満之 | (青森県) | 25cm反赤 | CCD画像1 |
| 福井 英人 | (京都府) | 25cm反赤 | CCD画像2 |
| 森田 光治 | (滋賀県) | 20cm反赤 | CCD画像6 |
| 柚木 健吉 | (大阪府) | 20cm反赤 | CCD画像18 |
| 米山 誠一 | (神奈川県) | 20cm反赤 | CCD画像2 |
| Grafton, Ed | (米国) | 35cmSC赤 | CCD画像21 |
| Ng, Eric | (香港) | 30cm反赤 | CCD画像3 |
近年のアマチュア観測機材の向上により、土星面では過去に観測されなかったような微小な斑点が頻繁に捉えられるようになっている。 今月もそのような模様がいくつか観測されていて、土星面がこれまで考えられていたよりも活動的であることをうかがわせている。
4日のGrafton氏の画像では体系III:45°付近のSTZに白斑が見られる。 また、30日の同氏の体系III:195°を中心とする画像では、STZとSTrZにひとつづつ、SEB内に2つと、4つもの白斑が一度に捉えられている。 これらは8分をおいた別の画像でわずかに位置を変えているため、どれも画像処理などによるノイズではなく、実在の模様と考えられる。 池村氏は7日に体系III:230°付近のSEB中央部に淡い小暗斑と周囲の軽い濃淡を捉え、自転によって土星面を移動する様子をアニメーションにまとめている。 これらは30日のGrafton氏の捉えたSEBの模様と近い経度にあるが、同一のものかどうかは不明である。
阿久津氏は土星では珍しいメタンバンド(893nm)による撮像を行っている。 この波長での土星面は、EZが明るく見え、SEBと極地方が暗い。 これらは可視光での特徴と概ね一致するが、可視光ではSEBの南半分が淡化し、ベルトが細くなっているのに対して、メタンバンドでは通常の太さに見えるのが興味深い。
(12月10日 堀川)
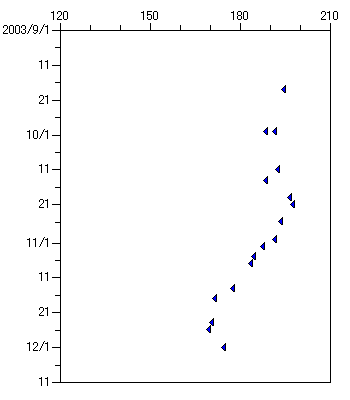 |
| 図1 mid-SEB outbreakの発生源の移動 |
|---|